独占禁止法。それだけ聞くと、市場を独占している企業は独占禁止法を適用されそうな気がするのですが、そうであれば独占禁止法を適用される企業などは沢山ありそうですよね。実際に独占禁止法が適用される際には、ただ市場を独占しているというだけでなく、その独占的な地位を利用して競争を排除・制限した場合に適用されます。

独占禁止法って名称だから独占したらダメだと思うよね



名称だけをみると、確かにそう思ってしまうよね
独占禁止法で問題となるのは「行為」であり「地位」ではないとされています。独占禁止法(Antimonopoly Act)では、市場支配的な地位を持つこと自体は違法としていません。つまり、製品が高性能である事から必然的に需要が高まり、その製品が買われ続けて市場のシェアを独占する状態になること自体は、製品が優良であるだけであって独占禁止法とはならないです。
ただ、やはり市場を独占するとその影響力が強くなってしまう事から、ある一定の市場シェアを占めるようになると監視(独占禁止法の適用条件)が厳しくなっていきます。国によって違いがありますが、日本だと市場シェア50%以上、欧州だと40%以上、米国だと70%以上になると、支配的地位があるとみられますが、それだけで独占禁止法が適用されるということではないです。
では、どのような状態になると独占禁止法となるのかというと、一定の市場シェアがあり、その地位を利用して競争を除外するような行動があった場合に該当となります。具体的には、他社と取引したら商品を売らないなどの「排他的取引」、人気商品と一緒に不人気商品も同時に購入させる「抱き合わせ販売」、競争相手を弱らせるために原価割れで販売する「不当廉売」、大量購入や長期購入を強要する「市場支配的地位の濫用」、競合や将来の潜在的競合を買収して市場支配力を強化する「企業買収による競争排除」などがあります。
エヌビディアのような半導体市場をほぼ独占している企業であっても、エヌビディア製品が市場シェアを独占している事じたいは問題ではなく、その状態で他社に圧力を掛けているかどうかが問題となっていきます。今回、中国がエヌビディアに独占禁止法を適用したのは、競合や将来の潜在的競合を買収して市場支配力を強化する「企業買収による競争排除」という事になります。
エヌビディアのように市場を独占する状態になってしまうと、どうしても独占禁止法の網が掛かってしまいます。自社の力を強くしようと思うと技術力のある企業を買収しようとするのは当然の企業戦略なのだけど、でもそれが「他社の競争力を除外する行為だ」と言われれば、確かにその通りですからね。問題は、どの程度の影響力があるかという事になるのだけど、その辺りは政治的な要因も絡んだりするので難しい判断になるよね。
大量購入や長期購入を強要する「市場支配的地位の濫用」についても、エヌビディアにはその気がなくても、エヌビディアの製品をどうしても欲しい企業は大量に買い付けるし、それが大量購入を強要しているとイチャモンを付けられる可能性もあり、また大量に買い付ける巨大テック企業ばかりに商品を卸して中小企業を後回しにしていると、今度は「差別的取引」と判断される可能性もあるから、本当にエヌビディアのように力をつけすぎた企業は対応に苦労すると思います。
マイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップルなど力を付けた巨大企業は、常に規制当局と独占禁止法で揉めています。エヌビディアも大きくなり過ぎた弊害として各国規制当局と独占禁止法でのバトルが起こるのは必然であり、仕方がない部分でもあると思います。
逆に言えば、これらの企業は必要とされている企業(製品、サービス)であり、代替えが難しいものであるからこそ、安定して成長していけると言えるのかもしれませんね。
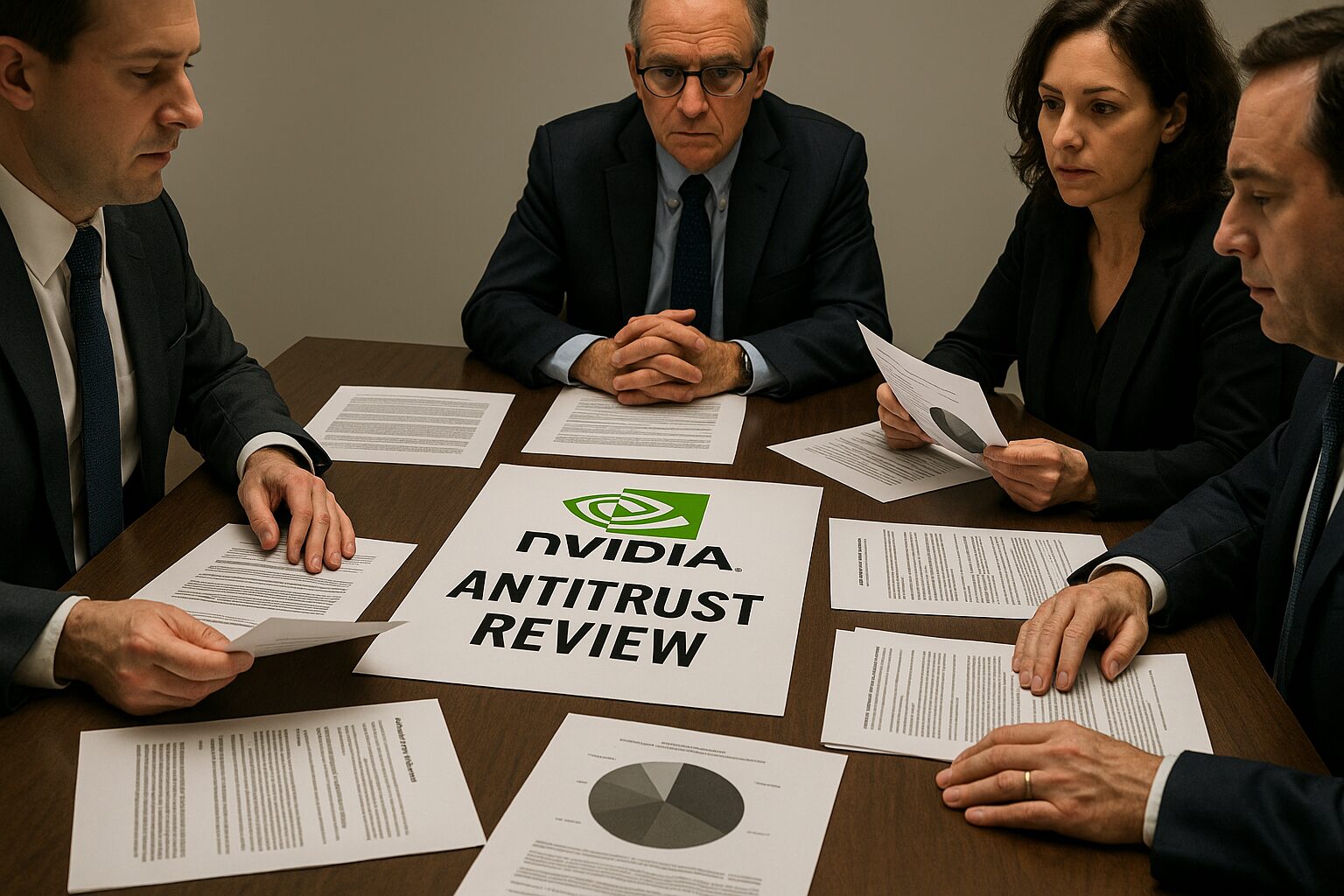

コメント